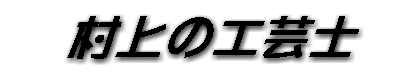 |
| INDEX |
|
高 橋 要 (号 連峰) |

伝統工芸士「高橋 要」 |
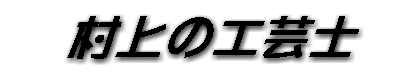 |
| INDEX |
|
高 橋 要 (号 連峰) |

伝統工芸士「高橋 要」 |

| 手先が器用だった要さんはお父様の勧めで堆朱塗師の道に入った。
師事した人は益子連雲と言い、私の曾祖父の弟にあたります。昭和初期の徒弟制度ですので、 最初は師匠の身のまわりのことや、家事などしかさせてもらえなかったそうです。3年経ってやっと 漆をさわらせてもらえるようになっても「これをしろ」と言うだけでどうすればうまくできるのか教え てもらえず、失敗すればおこられ、どうして失敗したかも教えてもらえず、そういうことは先輩の仕事 を見て覚えなければならなかったそうです。 負けず嫌いだった要さんは、「どうしたら能率良く きれいにできるのか」ということばかり考え、年期があける頃には、弟子の中で一番うまくなった のです。 一人独立して工房を構えた時も誰も仕事のことは教えてくれないので、「どうしたら艶が でるのか」など研究の毎日でした。 今では3人の子供達が堆朱の仕事をしており、後継者と いう点では心配ないのですが、棗の合い口など勘所は「自分でなければダメだ」と 生涯現役、生涯職人の方なのです。 要さんは木彫堆朱・ 木彫堆黒・木彫朱溜塗りの茶道具も広く手がけており、ここに紹介しているのはほんの一部ですが、 お客様に喜んでもらえる品物、お客様に満足して頂ける品物を作りつづけています。 |

| 大正 2年 | 朝日村猿沢に生まれる |
| 昭和 2年 | 堆朱塗師 益 子 連 雲 に師事。 |
| 昭和14年 | 独立して工房を構える。
堆朱求評会、各種漆器コンクール等入賞。 |
| 昭和51年 | 伝統工芸士の称号を認可。 |
| 昭和51年 | 卓越技能者として新潟県知事より表彰を受ける。 |
| 昭和54年 | 黄綬褒章受章。 |
| 昭和59年 |
産業の振興に対する貢献により 東京通商産業局長表彰を受ける。 |
| 昭和60年 | 産業の振興に対する貢献に
より 通商産業大臣表彰を受ける。 |
| 昭和60年 | 勲六等瑞宝章受賞。 |
[ 作 品 ]
 |
| 木彫堆朱棗(上彫り) | 木彫堆朱棗 |
 |
 |
| 110,000円 | 80,000円 |
| (高さ)7cm(幅)7cm | (高さ)7cm(幅)7cm |
| 技法 | |
|
木地に彫刻をし、漆を塗り重ねて仕上げる。彫刻があるため塗り方が
難しく、指頭、又はタンポで塗る。出来上がりは黒味がかった朱の色だが、年数が経つにつれ、艶が
出て輝く朱の色になる。 棗の場合は合い口が良くなるまで何度でも錆地をつけ、十分枯らして から研いで塗りあげる。 彫りは牡丹唐草が多く、上彫りは花の部分を細かい地紋仕上げにし、 立体感を出すために引き下げて彫っている。彫りが細かくなると塗りも数倍むずかしくなる。 | |
| 木彫堆黒棗 | 木彫朱溜塗り棗 |
 |
 |
| 80,000円 | 120,000円 |
| (高さ)7cm(幅)7cm | (高さ)7cm(幅)7cm |
| 技法 | 技法 |
| 木彫堆朱と同様に 塗り上げるが、黒漆を使い、黒仕上げで玄人好みと言える。ひき漆をしてみがいて艶を出して仕上げる 。 | 堆朱塗りの 上塗りの後、艶消しを施し、木地呂漆(最高級漆)を塗り仕上げ、全体が濃いチョコレート色をして いる。ひき漆をしてみがいて艶を出して仕上げる。 |
| 硯箱 | |
 | |
| 250,000円 | |
| (長さ)24cm(幅)18cm(高さ)6cm | |
| 技法 | |
| 真ん中で合わさる印籠ぶたの硯箱で、かぶせぶたの硯箱より数倍仕事が難しい。彫りは鳳凰の図で 引き下げられた部分は地紋彫りを施し、まわりは牡丹唐草である。 | |